 映画ルックバックを見ました。
映画ルックバックを見ました。
ちょっと前に書評(マンガ評?)で取り上げられてるのを見て原作を読んだのですが、それからの映画鑑賞。
なんか久しぶりに足しすぎず引きすぎずの映像化と言う感じでした。
あーあのシーンはもうちょっと欲しかったなーとか思わなくもないのですが、好きなシーンは人それぞれなのでね。
入場者特典でもらった冊子(Original Storyboard)が原作ネームととのことですが、他で見かけるネームよりも遥かに書き込みがあって大満足。
 映画ルックバックを見ました。
映画ルックバックを見ました。
ちょっと前に書評(マンガ評?)で取り上げられてるのを見て原作を読んだのですが、それからの映画鑑賞。
なんか久しぶりに足しすぎず引きすぎずの映像化と言う感じでした。
あーあのシーンはもうちょっと欲しかったなーとか思わなくもないのですが、好きなシーンは人それぞれなのでね。
入場者特典でもらった冊子(Original Storyboard)が原作ネームととのことですが、他で見かけるネームよりも遥かに書き込みがあって大満足。
 NakamuraEmi COTTON CLUB 「七夕はここで。~2024~」を見に行ってきましたよ。
NakamuraEmi COTTON CLUB 「七夕はここで。~2024~」を見に行ってきましたよ。
この日のオープニングはギターのカワムラヒロシさんとステージに登場して「メジャーデビュー」を歌いだしたので、"最初はギターと歌で何曲かやるのか?"と思っていたら、曲の途中で他のメンバーも入場し、演奏に参加。ってたしかにCDと同じなんだけどライブでやると効果的ですねこれ。
この日のメンバーは
NakamuraEmi (vo)
カワムラヒロシ (g)
内田匡俊 (b)
深谷雄一 (ds)
片木希依 (p)
のみなさんで、前回見たバンドセットとも違うメンバーだし、ベース、ドラム、ピアノの3人は地方からの参加というのがすごいというか、リハなんかもあるしよく集められるなぁと変な感心をする僕。
今回の選曲は全アルバムから一曲以上いれているらしく、最近のアルバムしか聞いていない僕が知らない曲も散見。
昔は知ってる曲じゃないとイマイチ、と思っていたこともありますが、今は知らない曲のほうが楽しかったりもするので、人って変わるもんですね。
当日のセットリストをストリーミングサービスのプレイリストとして公開するの気が利いていて良いと思います!
https://music.apple.com/jp/playlist/nakamuraemi-cotton-club-%E4%B8%83%E5%A4%95%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A7-2024-day2/pl.7c9ec4f519404c1b93fd736c5d6b285a?itsct=music_box_link&itscg=30200&ls=1&app=music
 高野 史緒のグラーフ・ツェッペリン あの夏の飛行船を読みましたよ。
高野 史緒のグラーフ・ツェッペリン あの夏の飛行船を読みましたよ。
シンプルに言うとタイムトラベル・パラレルワールド・ボーイミーツガール物ですね(そんなの初めて聞いた)
あまりにもシンプルに纏めてしまったので自分でも驚いておりますが、とは言えパラレルワールドとわかるまでの細かい描写であるとか、後半の飛行船が!!と言う手に汗を握るシーンなんか読んでいて楽しいのです。
これを読んで思ったのは、他の並行世界では、インターネットとかITがあまり進んでいないものの、他の星の開発は進んでいる世界というのが出てきて、そう考えると科学技術の分野ごとの進歩が違うって考えるとなんか面白い。
やっぱり夏はSFですよね。

 白洲 梓の魔法使いのお留守番を読みましたよ。
白洲 梓の魔法使いのお留守番を読みましたよ。
魔法使いファンタジーっていうんでしょうか?僕が普段読まないタイプの小説。
ざっくりいうと子供の魔法使いが伝説の魔法使いのもとで育つの?と言う話で、読みやすいです。
そして、オレンジ文庫という集英社のライト文芸レーベルっぽく、ちゃんと登場人物の青年2人はイケメンの設定になっています。
なんかですね、地の文と会話の文のミスマッチがちょいちょい気になって集中力が途切れたりするんですが、それはもう歳を取ったってことですよね。
 恩田陸の灰の劇場を読みましたよ
恩田陸の灰の劇場を読みましたよ
これ実在の三面記事をヒントに作られた話らしいのですが、話の構造がちょっと面倒で面白い。
作者本人と思しき人(「私」)の記述で進むのですが、更に芝居の話も絡んできたり、「私」の考えたニュースの元になった女性たちの生活もリアルに書かれたりして、実は本当の話?と思ってしまう感じ。
この人の小説は面白い思想が書かれていたりするのですが、この本には「地方出身者が東京を目指すのは、とにかく匿名になりたい」という記述があって、"あ、そうか有名になりたい人も東京を目指すし、匿名になりたい人も東京を目指すのか"と、今までちょっともやっとしていたことが明文化されてすっきり。
 絲山 秋子の神と黒蟹県を読みました。
絲山 秋子の神と黒蟹県を読みました。
黒蟹県という架空の県に神が一般人に化けて住んでいると言う話。
というと結構浮世離れした話かと思いきや、意外と地に足のついた話でした。
県全体というか県の一部の町の細かいところ、あの町とは仲良くないとかあの蕎麦屋がうまいみたいな細部の作り込みが面白く、更にそこに絡む人に関する書込みが細かくて結構好き。
一番好きなのは各短編のあとにある注釈には[架][実]とアイコンが付いていて、架空のもの、実在するものがちゃんと分かるようになっているところか。
内村さま~ずのシリーズが好きでずーっと見ていた(Netflixに入ってないので今は見られていない)僕なのです。
番組中でちょいちょい内村、さま~ずのお互いの単独ライブのお知らせがあって、いつか見てみたいと思っていて、先日チケット先行販売のお知らせがちょうど目に止まり、見に行くことに。
昔からコントに定評のあるさま~ずなので面白いのですよ、あの内村さま~ずのゆるい感じかと思ったら、結構かっちりしたコントが多くて"東のコントの人たちだ!"という感じ。
そして何よりもセットがすごい。コント事に違うセットがきっちり組まれていて、ホリプロさすがですわ、と思いました。
こう言うライブを気軽に(チケット取るのは大変ですが)見に行けるってやっぱり良いもんですね。
 ONYX BOOX Go Color 7を買いましたよ。
ONYX BOOX Go Color 7を買いましたよ。
結構昔からKinde端末を愛用して2-3年間隔で買い替えていたのですが、2020年にPaperWhiteを買いちょっといまいちだったので、Oasisの新型でないかな―と待っていたのですがしばらく発売されなさそうなのでカラーでボタンの付いているこれが発表されたのでポチッと。
PaperWhiteだと画面のスワイプでページめくりなのですが、片手で持つとかなり不便なので、ボタンでページめくりは今回必須ということで。
[好きなところ]
・画面がでかいし、ギラギラしていないので読みやすい
・動作がきびきび
・SDカードが使える
・ボタンでページめくりができる
[好きじゃないところ]
・Kindleアプリはマンガのページめくりでスライドのトランジションが入るので
Kindle端末の良さというのは、読みやすさもあるのですが、メールとかメッセージとかそういった割り込みが発生しないところにあると思ってます。
その点だとこれはAndroid端末なので、メールもLineも使えてしまうわけですが、そこをあえて使わず書籍専用で使っていく予定。
ちなみに皆さん興味があると思うので一応伝えておくと、カラー表示は「...カラーだな」という感じです。
メーが―直販で$249.99-(送料$15.99-)
言いたくはないけど円安...と言う感じですね。
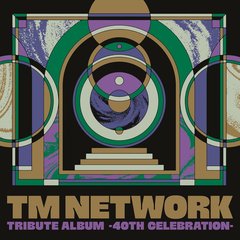 TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-を聞きましたよ。
TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-を聞きましたよ。
バラエティに富んだ人たちがTMの曲をカバーするというのがやっぱり面白い。
いろいろ面白いのですが、満島ひかりはアレンジの妙もあってすごい。松任谷由実もSKYEのアレンジでシティポップ風味になっているところがすごい。
カバーというのは演奏者(とスタッフ)の力量が露骨に見えちゃったりするので、こうやって並ぶと勉強になります。
原曲の入ってる2枚目は懐かしくてちょっと泣きました(笑)
 宇多田ヒカルのSCIENCE FICTIONを聞いていました.
宇多田ヒカルのSCIENCE FICTIONを聞いていました.
初のオールタイムベストと聞いて、なんかベストアルバムにもいろいろ種類があるのだなぁと、妙に感心。
ベストアルバムなんで聞いたことがある曲ばかりなのですが、再録音、リミックスも多く、それらの仕事も丁寧というところがさすがこの人という感じ。
しかも曲によってはちゃんとDolby Atmosになっているのがさすが。(と書いて気付いたのですがソニー所属なのに360 Reality Audioではないのか)
あ、コンサートのチケットははずれました。